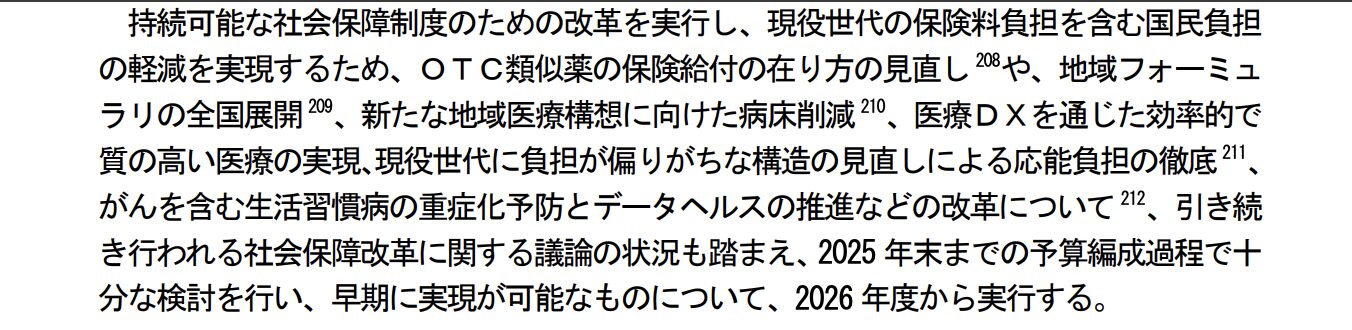まとめ
2025年、セルフメディケーション税制の見直し議論が再び活発化しています。 この制度は、対象のOTC医薬品(一般用医薬品)を購入した際、一定額を所得控除できる仕組みですが、利用率は依然として低く、制度の使いづらさや対象薬のわかりにくさが課題となっています。 さらに、政府は今後、「医療用医薬品と同成分のOTC薬がある場合、保険適用から除外する」方針を検討しており、軽症の症状については市販薬で自己対応する方向へ舵を切ろうとしています。 この記事では、制度見直しの背景と、これからの時代に必要な賢い市販薬の選び方を詳しく解説します。 |
セルフメディケーション税制は、自分の健康管理を目的に市販薬を購入した際、年間の購入額に応じて所得控除を受けられる制度です。
対象医薬品を年間12,000円以上購入した場合、その超過分(最大88,000円まで)が控除対象となります。
※参照:厚生労働省 セルフメディケーション税制の効果について 令和7年5月21日 税制のEBPMに関する専門家会合(令和7年度第1回)
しかしながら、利用率は依然として低い水準にとどまっています。
・レシート管理の手間
・対象薬がわかりにくい
・確定申告が必要であること
このような理由から、多くの人が制度を知っていても利用を見送っているのが現状です。
こうした低利用の実態を受け、政府は2025年度に以下のような見直しを検討しています。
制度改善の方向性
対象医薬品の拡充と表示のわかりやすさ向上
申請手続きの簡素化(マイナポータルや電子申告との連携強化)
保険診療からの除外(保険外し)の適用範囲拡大
特に注目されるのが、「医療用と同成分のOTC薬がある場合、医療機関で処方されても保険適用しない」いわゆる「保険外し」という動きです。
保険外しの対象例
・アレグラ(アレルギー薬)
・ガスター(胃酸分泌抑制薬)
・ロキソニン(解熱鎮痛薬)
これらの薬は既に市販薬として広く流通しており、将来的には「自己責任で購入すべきもの」とされ、医療費削減の一環として保険外扱いになる可能性が高まっています。
※参照:内閣府 「経済財政運営と改革の基本方針2025 ~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~」(令和7年6月13日閣議決定)
上記以外にも、医療用医薬品と同じ有効成分を含む「スイッチOTC薬」の対象が広がりを見せています。
中でも注目されているのが、最近発売されたPPI(プロトンポンプ阻害薬)と呼ばれるタイプの胃薬です。
PPIは、胃酸の分泌を強力に抑える作用があり、「逆流性食道炎」や「消化性潰瘍」などに使われてきました。
スイッチOTC化により、症状がよっては薬局での購入が可能となります。
医療費削減や患者の利便性向上が期待されています。
これからの時代、市販薬を”安いから”ではなく、”適切だから”選ぶことが重要です。
1. 対象医薬品かを事前確認
薬局やドラッグストアで「セルフメディケーション税控除対象」と明記されている商品を選びましょう。
パッケージやレシートに専用マークが表示されることが多く、厚生労働省の公式サイトでも対象一覧を検索できます。
※参照:厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
2. レシートの保管を習慣化
セルフメディケーション税制の適用には、対象医薬品の記載があるレシートが必要です。
大量のレシートがお財布やポケットから見つかると、つい処分してしまいがちですが、購入した内容を確認する習慣をつけましょう。
スマホアプリなどでレシートを撮影・保存しておくことも良い方法です。
3. 価格だけでなく”適合性”で選ぶ
同じ成分でも、錠剤・カプセル・散剤など、剤形が異なる場合があります。
自分の症状や服用のしやすさに合わせて選ぶことが大切です。
4. 薬剤師への相談を積極的に
市販薬を自己判断で選ぶのはリスクも伴います。
持病や他の薬との飲み合わせ、副作用のリスクを回避するためにも、薬剤師に相談する習慣を持ちましょう。
薬局は、単に薬を売る場所ではなく、生活習慣・服薬歴・健康相談を含めた総合的な健康サポート拠点です。
制度を理解し、薬局を上手に活用することで、医療費を抑えつつ健康を維持できます。
2025年以降、制度の変化はさらに加速する見込みです。
健康管理に必要な市販薬を賢く選び、正しく使い、制度を活用することが、家計と健康の両面であなたを守る最大のポイントとなるでしょう。
-1-e1690942602364.png?1769631606)

.jpg)